2024年6月26日放送のホンマでっか!?TVで最新の腸活について紹介されました!
教えてくださったのは、評論家の 池田清彦(生物学)、 井上亮(腸内細菌)、牛窪恵(マーケティング)、梶本修身(疲労)、 岸村康代(腸活栄養学)、桐村里紗(腸活)各先生です。
すべての健康は腸から!
最新の腸活・井上亮教授
井上亮教授は、日本人の腸内細菌について研究しています。腸内細菌は、私たちの体の中にたくさんいる小さな生き物で、健康に大きな影響を与えています。
井上教授の研究によると、日本人の腸内細菌は5つのグループ(タイプ)に分けられます。このタイプは、その人の健康状態や生活習慣と関係があります。例えば、バランスの良い食事をしている人は、良いタイプの腸内細菌を持っていることが多いです。
また、腸内細菌のバランスが崩れると、病気になりやすくなります。免疫力が下がったり、脳の働きが悪くなったりすることもあります。
そこで井上教授は、日本人の腸内細菌を調べるための大きなデータベースを作りました。このデータベースを使って、京都府立大学や株式会社プリメディカと一緒に、腸内環境を測る「Flora Scan」というシステムを開発しました。このシステムは、2023年に内閣府の賞やグッドデザイン賞をもらいました。

腸内環境を良くするには、発酵食品や食物繊維をたくさん食べることが大切です。特にナスには、腸に良い成分がたくさん入っています。
便秘の人は、腸内細菌のバランスが崩れていて、特にビフィズス菌が少なくなっています。日本人は欧米の人と比べて、もともとビフィズス菌が多いのが特徴です。
このように、井上教授は日本人の腸内細菌について詳しく研究し、健康のために役立てようとしています。腸内環境と健康の関係について、科学的な根拠に基づいて説明している、とても重要な研究者だと言えます。
記憶力が良くなるのも、腸内細菌のおかげ。認知症も予防します。池田先生によると、記憶は悪いことばかり覚えていることもあるとか。
桐村先生によると、キャベツばかり食べていても腸活にはよくありません。炭水化物抜きダイエットをすると便秘の原因になります。冷えたご飯はレジスタントスターチといい、腸活に向いています。でも、キャベツと冷や飯はさすがにいつも食べられませんね。
グアーガム分解物も、飲み物に入れると腸内細菌のエサになります。薬局やネットで売っています。軟便にも便秘にも予防効果が。睡眠にもいい影響があります。目覚めが良く回復が感じられます。
水溶性食物繊維としておすすめなのはもち麦。食物繊維がもち麦の中の方まで入っているのでおすすめ。冷凍してスープやサラダに入れても良いですね。
温泉に入るだけで腸内細菌が増えることも!別府温泉に7日間5つの泉源に入ると、炭酸水が一番ビフィズス菌が増加しました。
週に3回紫外線を当てる実験をすると、腸内細菌のバランスが良くなりました。肌が赤くならない程度に日差しに当たればOKな腸活日光浴。夏なら8分で大丈夫です。
タンパク質を取りすぎると、腸内細菌に良くないことがあります。便が臭くなり、筋トレは腸内環境も意識しましょう。タンパク質だけでも筋肉が付きづらくなります。
お腹がゆるい人は、パンを米に、うどんを蕎麦にしましょう。腸の過敏症の人はこの傾向が多いです。健康にいいはずが、フルクタンが分解されず大腸で発行してお腹がパンパンになってしまいます。麦をできるだけ避けましょう。
フルクトースを多く含むりんごは、下痢気味の方にはおすすめしません。
ただ、便がゆるい人のほうがモテるかも!「トイレ大丈夫?」と聞く男性のほうがモテます。デート中にトイレを我慢する人もいるからです。5人に1人がトイレを我慢しているというデータも。
パスタは硬めで。レジスタントスターチが多く含まれます。ぜひアルデンテで作りましょう。タピオカもキャッサバのデンプンを冷やすからいいですね。春雨も同じです。
小豆と芋のおむすびは、多様な食物繊維が取れておすすめ。炊き込みご飯にしましょう。
チーズ納豆トーストもおすすめ!全粒パンと納豆とピザ用チーズを載せてトースターで焼きます。食物繊維、納豆、タンパク質が一気に取れちゃいます。
小麦ふすまシリアルのデザートも美味しい!ヨーグルトとココアパウダー、はちみつを混ぜて、小麦ふすまのシリアルを加えましょう。乳酸菌とビフィズス菌、食物繊維も摂れます。
便移植も行われています。健康な人の便から良い腸内細菌を移植します。健康なスーパードナーからは200万円の値段がつくことも。
日本人の腸内細菌叢は、大きく5つのタイプ(エンテロタイプ)に分けられることがわかっています。それぞれのタイプには、次のような特徴があります。
1. タイプA:たんぱく質と脂肪の摂取が多い人に多いタイプ。アスリートに多く見られます。
2. タイプB:炭水化物、たんぱく質、脂肪をバランスよく摂る健康的な食事の人に多いタイプ。日本人に最も多いタイプです。
3. タイプC:炭水化物を多く摂り、他の栄養素が不足しがちな食事の人に多いタイプ。
4. タイプD:ビフィズス菌が多いタイプ。たんぱく質や脂肪に加え、砂糖の摂取も多い傾向にあります。日本人に特徴的なタイプです。
5. タイプE:脂肪が少なく、栄養バランスの取れた食事の人に多いタイプ。健康的な人に多く見られます。
腸内細菌のタイプは、普段の食生活と深く関わっています。バランスの良い食事を心がけることで、健康に良いタイプの腸内細菌を増やすことができるのです。
また、腸内細菌のタイプと病気の関係も明らかになりつつあります。例えば、タイプAやタイプDの人は、生活習慣病になるリスクが高いことがわかっています。
腸内細菌は体の健康に大きな影響を与えています。食生活を見直し、良い腸内細菌を増やすことが健康への第一歩と言えるでしょう。
あなたの腸内フローラ調べます!腸内細菌検査キット【腸内博士】
最新の腸内環境を整える3種類の炭水化物
腸内環境を整えるのに良い炭水化物には、主に3つの種類があります。
1. オリゴ糖
オリゴ糖は、ごぼうや玉ねぎに多く含まれる糖質の一種です。私たちの消化酵素では分解されにくいので、ほとんどが大腸まで届きます。すると、善玉菌の一種であるビフィズス菌のエサになって、その数を増やしてくれるのです。
2. 食物繊維
食物繊維は、野菜や果物、穀物など植物性の食品に多く含まれています。食物繊維をしっかり摂ることで、腸内細菌の種類が豊かになります。すると、何らかの原因で腸内環境が悪くなっても、元の健康な状態に戻る力が高まるのです。
3. 玄米などの茶色い炭水化物
白米の代わりに玄米や雑穀米を食べることで、腸内環境が整います。白米は消化吸収が早いのですが、玄米には食物繊維が豊富に含まれています。この食物繊維が腸内細菌のエサになり、腸の調子を整えてくれるのです。
このように、オリゴ糖、食物繊維、玄米などの茶色い炭水化物は、腸内細菌を元気にしてくれる働きがあります。毎日の食事に上手に取り入れて、腸から健康になっていきましょう。
最新の腸活・腸と脳の関係
最近の研究で、腸内細菌が私たちの直感力や判断力にも影響を与えていることがわかってきました。
フランスのINSEADとドイツのボン大学の研究チームは、101人の健康な男性を対象に実験を行いました。半数の参加者には7週間、プロバイオティクス(善玉菌)のサプリメントを与え、残りの半数にはプラセボ(偽薬)を与えました。
実験の前後で「最後通牒ゲーム」というゲームをしてもらいました。これは、一方のプレイヤーにお金を分配する権利があり、もう一方はそれを受け入れるか拒否するかを決めるゲームです。拒否すると両者ともお金がもらえません。
このゲームで、提案が不公平だと感じたときに拒否する程度を見ることで、人の公平感を測ることができます。
すると、プロバイオティクスを摂取したグループは、実験後に不公平な提案を拒否する傾向が強くなりました。一方、プラセボグループでは変化がありませんでした。
また、腸内細菌のバランスが崩れている人ほど、プロバイオティクスの影響を受けやすく、公平感が高まることもわかりました。
血液検査の結果、プロバイオティクスを摂取したグループでは、ドーパミンの材料になるチロシンというアミノ酸の量が減っていました。研究チームは、腸内細菌がチロシンを介して脳の報酬系に影響を与え、社会的な行動を変化させている可能性があると考えています。
このように、腸は「第二の脳」とも呼ばれ、腸内細菌が脳に信号を送ることで、私たちの直感や意思決定にも関わっているようです。バランスの取れた食事を心がけ、腸内環境を整えることが、健康な判断力につながるのかもしれません。
最近の研究で、腸内細菌が私たちの食べ物の好みや食欲に影響を与えている可能性があることがわかってきました。
腸内には数百種類、100兆個以上もの細菌が住んでいて、腸内細菌叢(そう)と呼ばれています。この腸内細菌は、食べ物を分解して栄養を吸収するのを助けるだけでなく、私たちの体や脳の健康にも関わっているんです。
例えば、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のエレイン・シャオ博士らは、特定の腸内細菌がセロトニンという神経伝達物質の生産を調節していることを発見しました。セロトニンは気分を安定させるのに重要な物質です。
また、ユニバーシティ・カレッジ・コークのジョン・クライアン教授らは、健康なマウスに特定の善玉菌を与えると、与えなかったマウスに比べてリラックスした行動を示したという実験結果を2011年に発表しました。
腸内細菌が脳に影響を与えるメカニズムはまだ完全には解明されていませんが、腸内細菌が作り出す物質が脳の神経伝達物質に作用したり、迷走神経を介して脳に信号を送ったりしているのではないかと考えられています。
もしかすると、私たちが無性に食べたくなるものは、腸内細菌が欲しがっている栄養素かもしれません。逆に、食べたくないと感じるのは、その食品が腸内細菌のバランスを崩すからかもしれません。
腸内細菌と脳の関係性を理解することで、食欲をコントロールしたり、肥満やうつ病などの治療法の開発につながる可能性もあります。
まだまだ謎の多い分野ですが、「腸は第二の脳」と言われるほど、私たちの心と体に大きな影響力を持っているのかもしれませんね。今後の研究の進展が楽しみです。
まとめ
みなさん、腸内環境を整えて健康的な生活を送りませんか?腸は第二の脳とも呼ばれ、免疫力や脳機能など私たちの健康に大きな影響を与えています。
腸活のポイントは、善玉菌を増やすこと。ヨーグルトや納豆などの発酵食品、オリゴ糖や食物繊維が豊富な野菜や果物を積極的に食べましょう。味噌汁は腸活の強い味方です。
また、適度な運動とストレス解消、質の良い睡眠も大切。腸内フローラを整えることで、便通の改善、肌の調子アップ、ダイエット効果など嬉しいメリットがたくさん!
さあ、今日から一緒に腸活を始めませんか?きっとあなたの毎日が健やかに輝き出すはずです。腸内環境を整えて、内側から健康美人を目指しましょう!
あなたの腸内フローラ調べます!腸内細菌検査キット【腸内博士】
関連記事:
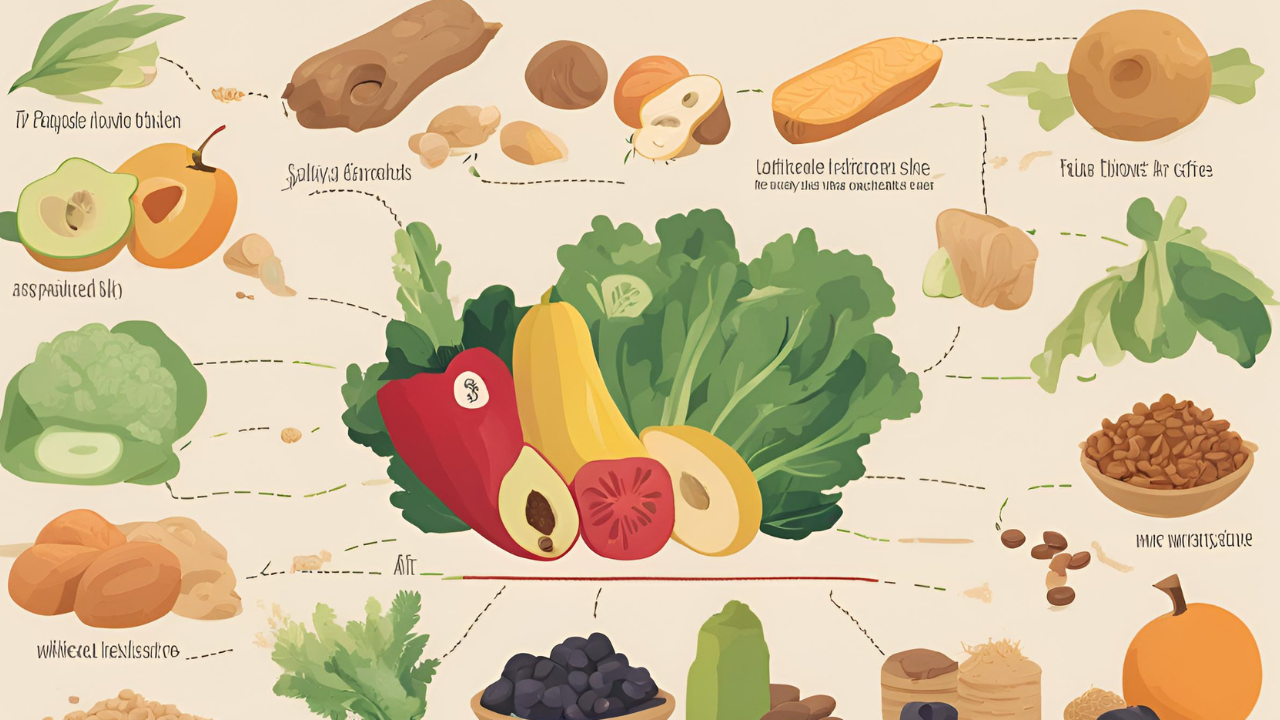









コメント